前回のコラムで、鼻腔共鳴を活かしたハミングが音程の安定に有効であることをお伝えしました。ここでは、「なぜ鼻腔共鳴の響きが音程を正確にするのか?」というメカニズムについて、さらに深く掘り下げて解説します。これから解説する内容は医学的、身体構造的には間違ってるかもしれませんが、歌唱時の体の内部の動きや影響をイメージしやすくするために大げさに表現しています。ご了承ください。
鼻腔共鳴とは
さて、本題に入る前に「鼻腔共鳴」について解説します。
「鼻腔共鳴(びくうきょうめい)」とは、発声時に鼻の奥にある鼻腔という空間を使って声を響かせる歌唱テクニックのことです。
声帯で発生した音が、鼻腔などの共鳴腔で反響することで、声に豊かさや響き、明るさが加わり、より遠くまで通るようになります。
歌唱に必要な共鳴区としてこの他に口腔、咽頭腔があります。そちらについてはまた別の機会にお話ししますね。
鼻腔共鳴が生む「高精度な音の確認、訂正の回路機能」
鼻腔共鳴が歌にもたらす効果は単に共鳴させて音を良くするだけではありません。「自分の出した音を高精度に確認して訂正する」ことにも大きく寄与します。このコラムをご覧いただくと、音程が捉えにくい方、自分ではぴったりの音で歌っているつもりでも音が下がってしまうなどの解決のヒントがみつかると思います。では、一緒に見てみましょう。
音の把握に時間がかかる喉声歌唱
多くの方が無意識に行っている喉声歌唱(口や呼吸口主体で、鼻腔をあまり使わない発声)の問題点の一つに、「自分の発声した音の把握に時間がかかる」があります。
喉声歌唱の音は次の順路で耳に届く傾向があります。
①口から外に出る
②空気を振動させる
③鼓膜を揺らして「自分の声」として認識する
喉声歌唱は「空気伝導」で自分の耳に届きます。イメージとして、体の中で作った音が一旦体の外に出て空気を伝わって耳に届く、なんとなく遠回りな伝わり方をしているように思えますね。体の中で作り出した音なのだから、体の中に響かせて、骨伝導で音を聴きとった方が効率的です。そこに、自分から出た声とその確認の動作にタイムラグが起きているのです。
脳が「この音を出せ」と指令を出し、声帯で音を作り、その音が外に出て、耳で拾われる、音のズレを感じる、修正する、までにおきるわずかな時差。それが歌唱、特に音程合わせに影響を与えます。
鼻腔共鳴で音程を捉える「骨伝導センサー」
一方鼻腔共鳴で歌う歌は「骨伝導」で自分の耳に聞こえやすく、雑音に惑わされずに自分の声を瞬時に聞き取り、音程を素早くコントロールすることが可能です。体の共鳴区を使って発声する歌声は骨を伝わって、骨伝導で直接内耳(蝸牛)に効率よく送られます。歌の上手い人は鼻腔共鳴を使って身体を最強の音響モニターに変えて歌っている、と言っても過言ではありません。
骨伝導がもたらす2つの効果
ダイレクトな聴取
空気伝導を通さず、体内で音が直接聞こえるため、タイムラグがほぼゼロになります。これにより、脳が意図した音と実際に出た音のズレを瞬時にキャッチし、修正する能力が飛躍的に向上します。
響きの質の確認
骨伝導によって響きを「体感」できるため、声に芯があるか、音程が安定しているかという「響きの質」を正確に把握できます。この体感によって、不安定な発声ではすぐに気持ち悪さを感じるようになり、自然と安定したピッチを追求するようになります。
音程コントロールを司る「筋肉の開放」
鼻腔共鳴を習得すると、喉周りの無駄な力みが取れ、音程の微調整を担う声帯のコントロール能力が高まります。
鼻腔共鳴が使えている状態は、共鳴腔に声を預けることができているため、喉仏(喉頭)が安定し、周囲の筋肉が緩んでいる証拠です。
このリラックス状態があって初めて、音程を高くしたり低くしたりする声帯の微細な筋肉(輪状甲状筋など)がスムーズに動き、0.1Hz単位での音程調整が可能になります。喉声で力んでいる状態では、この繊細なコントロールは不可能です。
鼻腔共鳴は、あなたの体を「高精度な発声モニター」に変える最も有効なトレーニングなのです。
音程の精密度アップを目指す方も、芸術的な表現を目指す方も、まずはこの「響きと音程のフィードバック回路」を鍛えることから始めてみませんか。
ハミングの基礎からゆるぎない声を育むボイストレーニングをご希望の方は
まきの歌広場公式LINEまでお問い合わせください。
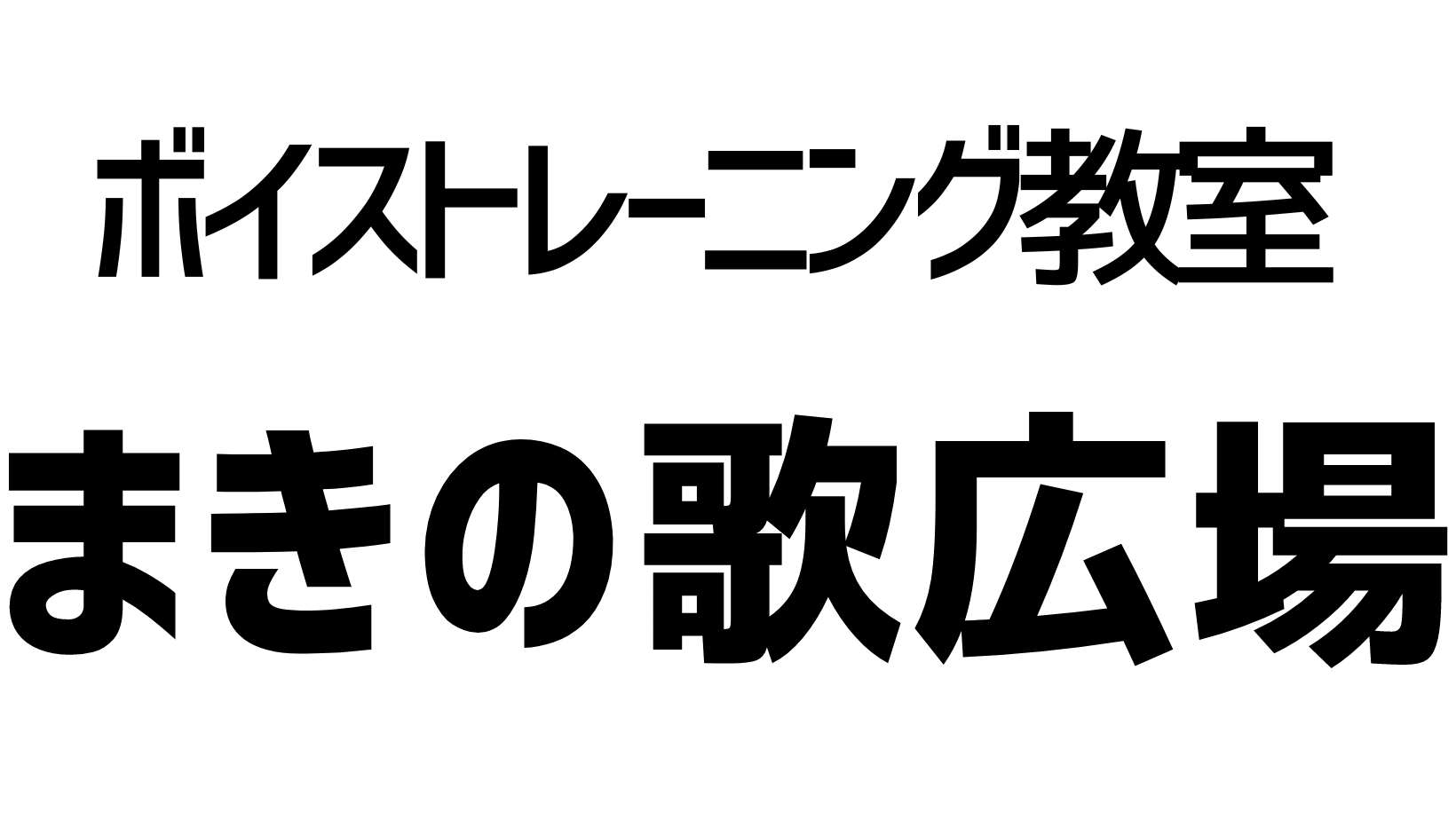













コメント